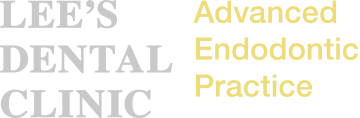LEE'S ブログ
根管治療に関する記事を中心に、専門的ながら大切なことを治療例をまじえて、一般の方にもわかりやすく解説しています。ありきたりな内容ではなく、欧米の論文を精読した内容をベースに信頼性のある有用な情報を発信するよう努めています。(*記事の元になっている引用文献を記載しています)
追記:多くのブログ記事の執筆当時からだいぶ時間が経過しております。最新の研究をもとにした現在の見解や治療のトレンドなどをアップデートできておりませんので、記事によっては当時の見解から変化している場合もあります。(2022.12.28)
皆様こんにちは。
生活歯髄療法の話をしばらく続けていきたいと思います。
神経に近い深い虫歯の治療、成功するか否かは神経の健康度合いと治療でぴっちり封鎖ができるかどうかがキモです。
歯の神経が健康かどうか、また歯の神経が死んでるかどうか、などを実際どのように診断するのか?
ということについて今日は書いていきたいと思います。
まず結論から申しますと、
歯の神経の生死を確実に知ることは実際に神経を見ないと不可能です。
神経が生きている、ということは神経に血のめぐりがあるかどうかです。
出血があると生きいるとわかるし、完全に死にきっていると出血しません。
実際に歯の神経を見るとは、歯を削って神経を露出させることになります。… 続きを読む
今日は生活歯髄療法についてもう少し書いていきたいと思います。
巷で有名なドックベストセメントや3-Mixを使った深い虫歯の治療も生活歯髄療法といえます。
神経を助けたくてドックベストセメントの治療を受けたのだけれども治療が失敗し、結局神経は助からなかった、ということで神経を取る処置のためにリーズデンタルクリニックに来院される患者様がいらっしゃいます。
お話を聞くとドックベストセメントや3-Mixはそれ自体を使うことで、深い虫歯に侵された神経が助かると勘違いされていることがほとんどです。
けれどもそうではありません。薬剤だけで効果があるならドックベストセメントの治療は失敗しないはずです。… 続きを読む
昨日から私が勤務医の時にお世話になった元上司の先生のカンボジアの歯科医院と診療を視察にきています。日本やアメリカ、カナダなど、先進国の歯科医療はよく理解していますが、開発途上国の歯科医療は初めてです。滞在中は現地で歯科医としてのボランティア活動も行う予定です。また帰国後にブログでご報告したいと思います。
さて、前置きが長くなりましたが神経に近い、深い大きな虫歯の治療法、生活歯髄療法について今日は書いていこうと思います。以前にも生活歯髄療法についてはブログで記事を書いていますが、9月に札幌のAE(Academy of Endodontics)での認定医更新試験のための発表で生活歯髄療法をテーマに選び、新たに80近くの関連論文を読み、新しい知識をアップデートすることができましたので、このブログで数回に分けてこのテーマを取り上げていこうと思います。… 続きを読む
こんにちは。李です。
今週は桜が満開でキレイでしたね〜

皆様はお花見にいかれましたか?私は近所の桜を散歩やジョギング中に満喫しました。
引っ越しをしてはじめての春でしたので、桜スポットを発見するのも楽しかったです。
なかでも一番綺麗だったのは茅場町のさくら通りです。桜の天井状態が続いていて桜スポットとしておススメです。とくに夜が綺麗です
 桜通りの写真です。
桜通りの写真です。

お近くの方はぜひこの通りをあるいてみてくださいね
さて、今日は生活歯髄療法Vital Pulp Therapyのパート3として、実際の治療法について簡単にお話していこうと思います。
VPTは大きくわけて2種類の治療法があります。… 続きを読む